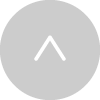株式会社静鉄リテイリングは、地域の社会問題の解決をテーマに、静岡県立駿河総合高校の「課題研究授業(商業)」に協力・参画しています。この授業では、高校生が地域課題を調査し、その解決策としての事業アイデアを考え、実際に商品企画や販売を行うことで、実践的な学びを得ています。
本記事では、この取り組みを担当する望月恭兵さんに、プロジェクトの背景や、高校生とともに企画に取り組む中での想いを伺いました。
■この取り組みが始まった経緯を教えてください。
静岡市の紹介を受けて、静岡県立駿河総合高校の「課題研究授業(商業)」に参画することになりました。 2024年度で4年目となったこの取り組みは、高校生が地域社会の問題をテーマに新たな事業アイデアを創出し、職業観を深め、地域創生に向けた創造力を高めることを目的としています。最終的には、静鉄リテイリングが運営するハンズ静岡店や各施設・店舗において、生徒発案の商品販売や企画アイデアの実現化まで連携しています。
■生徒発案の商品などが実際に店頭で販売されるのですね。
そうですね。生徒たちは地域の課題を調査するだけでなく、自ら解決策を考え、実際に行動することで主体性を養うことを目的としています。 2024年度は、「ロスフラワーを活用したアロマワックスバーワークショップ」と、「規格外農作物を使用した和紙しおり『いろはおり』の企画販売」をハンズ静岡店で実施しました。生徒たちが現場でお客様と直接関わることで、商品販売の実践的な経験を積むとともに、地域課題への理解を深める機会にもなっています。
【2024年度の取り組み――フードロス・フラワーロスに挑戦】
日時:2025年1月11日(土)、12日(日)
場所:ハンズ静岡店(新静岡セノバ3階)
①「ロスフラワーを解決!アロマワックスバーワークショップ」
市場に出荷できない規格外の花を有効活用し、アロマワックスバー作りを体験できるワークショップを開催しました。
生徒たちは、静岡特産のガーベラの生産現場を訪問し、フラワーロスの現状やその影響について学習。 そこで得た知識をもとに、花を無駄にせず、新たな価値を生み出す方法を模索しました。
ワークショップ当日は、来店されたお客様にフラワーロスの実態やその背景を伝えながら、アロマワックスバーの制作をサポート。 生徒たち自らが学んだことを伝えながら、花を再活用するアイデアを広める場となりました。


②「規格外農作物を使用した“いろはおり“の販売」
市場に出回らない規格外の野菜や果物を活用し、特製の和紙しおり『いろはおり』を制作・販売しました。
事前学習として、生徒たちは「しずおかもったいないプロジェクト」を運営する辻田氏の特別授業を受講し、フードロス問題について理解を深めました。その後、実際に農家を訪問し、静岡特産のみかん、葉ねぎ、石垣いちごなどの規格外作物を提供いただき、それらを和紙の原料として活用しました。完成した「いろはおり」は、ハンズ静岡店で販売。生徒たちは、商品の背景やフードロス削減の重要性をお客様に直接説明しながら販売活動を行いました。 商品を手に取るお客様との対話を通じて、フードロス問題への意識を広める貴重な機会となりました。


■高校生と企画を進めるうえで意識した点を教えてください。
この取り組みは高校の授業の一環であり、限られた授業時間の中で進める必要があったため、常にスピード感を意識しながら進行することを大切にしました。 その中でも、生徒の意見を最大限に尊重し、できる限りアイデアを実現できるようサポートすることを心がけました。


■最後にこの取り組みへの想いを聞かせてください。
この取り組みを通じて、生徒の皆さんに「実際の現場に足を運び、自らの目で見ることの大切さ」を伝えることができたと感じています。座学では理解しにくい課題も、農家の声を直接聞き、規格外品の現状を目の当たりにすることで、より深く学ぶことができます。こうしたリアルな体験を通じて、地域とつながることの意義を実感してもらえたのではないかと思います。
また、今回の「食品をモノに変える」という高校生たちのアイデアは、私たちや農家の方々にとっても新たな気づきをもたらしてくれました。 高校生が地域の課題に向き合い、創意工夫を凝らしながら形にしていく姿勢は、地域にとっても大きな財産です。
高校生が地域と関わることで、互いに学び合い、より良い地域づくりにつながることを願っています。 そして、この経験が彼らにとって貴重な成長の機会となり、未来の地域を支える人材へと育っていってくれたら、とても嬉しく思います。